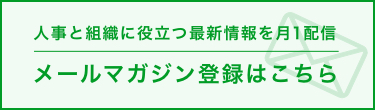コラム
コラム
ミドル・シニア人材活用――35歳限界説を超え、企業の力へ

企業の採用担当者にとって、今ほど頭を悩ませる時代はないかもしれません。新卒・中途採用の枠にとどまらず、未経験者や第二新卒、さらには外国籍人材の受け入れまで、あらゆる選択肢を駆使してもなお、「人が足りない」という悲鳴があちこちから聞こえてきます。皮肉なことに、「残業しない働き方」を推進するはずの人事部門が、最も残業に追われている――そんな現場の声も珍しくありません。
この採用難の時代、静かに存在感を増しているのが、ミドル・シニア人材です。豊富な経験を持ち、現場の即戦力となり得る彼らをどう活かすか。それは今後の企業競争力を大きく左右するテーマとなっています。
「35歳転職限界説」はもはや過去のものか?
つい最近まで、日本の転職市場には「35歳転職限界説」と呼ばれる暗黙の了解がありました。
採用活動で年齢制限を設けることは原則として禁止されているものの、実態として一般的な求人広告には20代の社員ばかりが登場し、応募要件に年齢制限は書かれていなくても、企業が求めているのは明らかに若手――そんな風潮がありました。
しかし近年、この状況に変化の兆しが見え始めています。株式会社マイナビの調査『転職動向調査2025年版』によれば、2024年における正社員の転職率(労働者全体に占める転職者の割合)は20~30代の割合が減少し、40~50代が増加しています。
「マイナビ 転職動向調査2025年版(2024年実績)」 https://www.mynavi.jp/news/2025/03/post_47937.html
40代以上のミドル・シニア世代の転職可能性が増したことで、経験豊富で企業価値に貢献できるような人材が、新たな機会を求めて転職市場に出てくるようになってきました。これはまさに、「35歳限界説」が少しずつ過去のものとなり、ミドル・シニア世代からの転職の可能性が高まってきたことを示唆しています。企業は、この変化を人手不足対策の一環として活用すべき時が来ているのかもしれません。
市場を動かす現場のリアル:“転職する事情”の変化と法改正
この変化の背景には、ミドル・シニア層側の“切実な事情”もあります。筆者の知人である54歳の男性は、長年勤めた企業で役職定年を控え、収入減が避けられない状況にありました。一方で子どもはまだ高校生で受験期。教育費のピークと重なるなかで、家計を支えるための転職を決断したと語っていました。
バブル崩壊後の景気低迷期に就職した団塊ジュニア世代の多くは、十分な昇給を経験していません。晩婚化によるライフイベントの後ろ倒しや物価高も重なり、50代以上でも「まだまだ働き、稼ぎたい」というニーズが増加しています。このように、単なる再就職ではなく“人生戦略”としての転職が活発になっているのです。
前述のマイナビの調査でも、転職理由・転職先企業の決定理由は「給与」が最も高い割合を占め、実際に転職によって、一部の年代を除き前職よりも平均年収が増加したとしています。
こうした動きが、ミドル・シニア世代の転職の増加に繋がっていると言えるでしょう。
企業側の事情も無視できません。日本全体の労働力人口は過去10年で約200万人減少し、今後も減少傾向は続く見通しです。一方で、50~60代の人口はむしろ増加しており、2025年には高年齢者雇用安定法の改正により、65歳までの雇用確保措置が強化されます。企業がこの年代の労働力を本気で活用し始める素地は、すでに整っているのです。
特に人手不足が深刻な業界では、若手人材の採用・育成にかかる教育リソースを割く余裕がない企業も多く、即戦力として早期に活躍してくれるミドル・シニア層の”経験”と“実力”に期待が高まっているのです。
ミドル・シニア人材の「強み」を活かす採用戦略
どのような業種業界でミドル・シニア人材が求められているのでしょうか?
たとえば、ある大手商社では、業界経験30年以上のミドル人材を新規事業部門に登用し、その人脈と経験が短期間での顧客開拓に大きく貢献しました。「新卒では到底開けなかった扉が、彼の一本の電話で開いた」という営業担当の言葉が印象的でした。
また、ある地方の介護施設では、60代の元不動産管理会社勤務の男性を施設長に採用。建物管理やスタッフとの調整、地域自治体との交渉などでその経験が生かされ、施設の運営効率が大幅に改善されたといいます。
年齢よりも“何ができるか”に着目した結果の成功例です。
その他、GX(グリーントランスフォーメーション)への対応が急務となっている中小製造業では、省エネや環境配慮設計に関する知見と経験を持つシニア人材が、実務を主導できる即戦力として重宝されています。
採用後の「定着」と「活躍」を促すための工夫
しかし、ミドル・シニア人材を採用できたとしても、そこで終わりではありません。
特に注意したいのは、“過去の成功体験”が障壁になるケース。「前の会社では…」という言葉が頻繁に出るなど、前職でのやり方に固執することで、今の職場とのギャップに適応できない例などはよく目にします。
彼らに定着し、そして最大限に活躍してもらうためには、いくつかの工夫が必要です。できれば人事部門を中心に、ミドル・シニア人材向けのプロジェクトを立ち上げるのが理想でしょう。
最も重要な工夫の一つは、「新たな採用プロセスの準備」です。
前職での経験が障壁とならないよう「仕事のスタイルが自社の風土や職種に合うか」を見極める上で有効なのが「適性検査の活用」、特に「性格検査の読み込み」です。若手人材の採用でも適性検査を活用する企業は増えていますが、多くは能力的な部分を判断材料にしています。しかし、ミドル・シニア人材の場合は職務経歴があるため、能力については若者よりも把握しやすいです。そのぶん、自社の風土や職種への適応可能性を見極めるための性格検査に時間をかけ、深く読み込むことが有効です。
さらに、人事制度面での工夫も欠かせません。具体的には、ジョブ型の評価制度を導入するなどし、職務・成果・責任を明確化することで、納得度の高い評価と処遇が可能になります。これにより、年功序列に馴染んだ人材でも、成果を出せば報われるという安心感が醸成され、意欲と成果の好循環が生まれます。
しかし、適性検査の読み解きや人事制度の設計といった難易度の高い施策は、自らも人手不足を抱える人事部門にとって、さらなる負担になりかねないという懸念もあります。無理に自社だけで完結しようとせず、採用から定着、活躍までを並走してくれるような人事コンサルティング会社を頼るのも有効です。
経験は“足し算”ではなく“掛け算”になる
ミドル・シニア人材は、単なる“人手の補填”ではなく、企業の新しい成長戦略の核となる存在です。採用トレンドの変化と現場ニーズの変化が重なり、いまや「35歳限界説」は過去の神話となりつつあります。
豊富な経験、実績、そして広い人脈。これらをどう活かすかは、企業の姿勢次第です。ミドル・シニア人材を“戦力”として迎える準備を整えること。それが、これからの企業の競争力を高めるカギになるはずです。