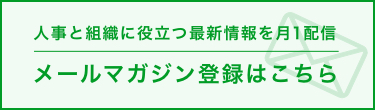コラム
対談企画
企業価値の向上と関連性が高い「役員報酬」の決め方と見直しのトレンド

役員報酬とは、その名のとおり取締役や監査役といった役員の責任や役目を果たしていることに対して支払われる報酬です。社員から役員に任用されるケースも多く、報酬の決め方など同じように行われている企業もあります。一方で責任も大きく、雇用が守られている訳ではありません。成果に対する対価の考え方も違っていて当然です。そこで、役員報酬の制度構築に関して、妥当な設計のために外部コンサルティング企業を活用するケースが増えてきています。そのような背景など役員報酬・株式報酬制度コンサルティングを専門とするO f All株式会社の代表取締役 福地悠太様にお話しを伺いました。
※セレブレイン社はO f All社と連携して、企業の役員報酬制度構築のご支援を行っております
高城:役員報酬制度について、通常の社員向け人事制度との違いを教えてください
福地:役員報酬は、会社法や税法上の取り扱いが従業員の給与とは異なるため、法務・税務的な観点でも設計上の留意点が異なります。また、役員の報酬は業績や企業価値とより連動した報酬体系とすることが求められており、経営戦略上の目標達成や投資家を含むステークホルダー全体との利益共有といった、より大きな視点での設計と運用が必要になってくる点が、社員向けの人事制度と大きく違う部分だと考えています。特に、外部株主がいる企業や株式公開をしている、または株式公開を目指す企業については、ステークホルダーとの利益共有を意識した報酬設計は必須と言っても過言ではないでしょう。
具体的には、月次の固定報酬、業績連動金銭報酬、自社株式や新株予約権を用いた株式報酬それぞれの額やバランスをどう考え、報酬総額の適切な水準を設定するのか、また、業績連動報酬や株式報酬はどのような支給条件を設けるのか。これらを経営戦略上の目標達成へのインセンティブ付けやステークホルダー全体との利益共有といった視点で十分な検討を行う必要があります。
高城:役員報酬・株式報酬を取り巻く環境変化はあるのでしょうか?
福地:日本企業の役員報酬は、欧米諸国に比べて低い水準にあると言われており、政府や東京証券取引所はこの点を問題視しています。グローバルで優秀な経営者を獲得・維持できない企業が多いということであり、ひいては日本企業全体の競争力低下にもつながると捉えているからです。そのため、2016、2018年に役員報酬に関する法改正が行われており、譲渡制限付株式と言われる現物株式を報酬として支給する制度の法的論点が明確化された他、業績連動報酬として損金算入が可能となる要件が緩和拡大されるなど、特にインセンティブ報酬の導入がしやすくなっています。また、東京証券取引所もコーポレートガバナンスコード(以下CGCという)において、役員報酬として業績連動報酬や株式報酬の導入検討を求めています。その一方で、この機に乗じた根拠ない役員報酬の増額、いわゆるお手盛りで報酬額を決定することには警戒感を示しており、役員報酬の決定プロセスについて、報酬委員会の設置を含めた、社外役員その他外部の視点を取り入れた報酬設計を行うことも同時に求めています。

高城:役員報酬制度設計について、多くの企業から問い合わせをいただくようになってきており、外部に委託する必要性が高まってきていると感じています。そのあたりの背景について、お感じになっていることを教えていただけますでしょうか?
福地:今まで日本の多くの企業は、代表取締役の感覚に頼って役員報酬の金額が決まってきたところが多分にあります。また、役員の報酬体系が定期的に見直しされる企業もあまりなく、前年報酬を引っ張るもしくは前年報酬額から業況に応じて増減するなどの運用が多く見られました。しかし、人材・報酬マーケットが大きく変化する昨今、このような報酬体系と運用では、優秀な経営人材を外部から獲得することは困難となり、また自社の優秀な役員が流出するリスクも高まってしまいます。元々いた役員の報酬水準とはかけ離れた金額で新たな役員を迎え入れるといった対応もあり得ますが、場当たり的な対応を重ねた結果、役員間での不和やハレーションを引き起こすといったリスクも当然生じます。そのため、報酬マーケットのデータをインプットした上で、自社の経営を任せるに足る人材を維持し適切なインセンティブ付けをするためには、報酬の水準や構成その詳細な内容をどう定めるべきか、制度として設計をして定期的にアップデートしていくことが必要になります。
高城:役員報酬設計でよく起こる問題点を教えてください
福地:よく起こりがちなのは、これまでの報酬水準に囚われすぎるという点です。当然今までの報酬から大きく変動するとなると、下がる場合は生活給的な観点で困る方もいますし、上がる場合は企業のP/Lへの影響を懸念するといったこともあるでしょう。もちろん設計の際にはそういった点を考慮すべきであり、場合によっては段階的に報酬額を変化させるような経過措置的な仕組みを取り入れることもあります。ただ、今の報酬水準に強くこだわりすぎてしまうと制度を改定する意義が失われてしまいます。そのため、中長期的に企業価値を伸ばすには、どういった報酬体系であるべきか、という視点をぶれない軸として持ち、短期的な影響を許容範囲にとどめるための仕組みも必要に応じて検討するといったスタンスが必要になります。
また、株式公開している上場企業に限った話になりますが、有価証券報告書に個別報酬額の記載義務が生じる1億円を超えないことを目的化してしまうといったケースもあります。企業規模が拡大すれば報酬額が1億円を超える役員が出てくることも必然と言えるので、むしろ堂々と報酬額が1億円を超えていることを開示できるよう、役員報酬制度をきちんと合理な内容で作りこんでいくことが必要なのではないかと個人的には考えています。
高城:役員報酬の相場について(ベンチマーク)の適切なすすめ方について、教えていただけますでしょうか
福地:例えば、こちらは当社が収集している2024年の「上場企業全体の役員報酬に関するデータの平均」をまとめたものです。
|
|
取締役(社外除く) |
社外役員 |
|
役員報酬総額 |
193,621,023 |
31,730,925 |
|
固定報酬総額 |
123,937,551 |
30,958,341 |
|
業績連動報酬総額 |
38,155,458 |
266,112 |
|
株式報酬総額 |
28,090,330 |
382,840 |
|
役員1人当たり報酬総額 |
35,824,407 |
5,713,384 |
|
役員1人当たり固定報酬額 |
23,648,864 |
5,577,082 |
|
売上高に対する役員報酬総額割合 |
0.83% |
0.17% |
|
営業利益に対する役員報酬総額割合 |
28.94% |
5.77% |
こういった外部データとの比較を行うことが必要となりますが、ここまで広い括りと比較をしてしまうと無意味とまでは言いませんが、適切な比較にはどうしてもなりづらくなります。業種やビジネスモデルが自社に類似している、規模や収益水準が自社の現在値から中長期で目指す水準のレンジ内または上限下限に近い、といった視点で絞り込みを行い、特定のピアグループやベンチマークの報酬体系をきちんと分析していくことが重要になります。
また、その分析を通じて役員報酬相場を理解した上で、自社のあるべき姿を実現するためにその相場(=報酬マーケット)をどう捉え、自社の報酬は相場に対してどうあるべきなのかをしっかりと考えていくべきです。
加えて、自社のフェイズや中長期の戦略として、現在上場企業で今後も継続して上場企業であるのか、上場準備企業であるのか、非上場かつ今後もそれを継続するのかといった部分も勘案し、報酬水準やその構成について検討する必要もあるでしょう。
お伺いした方:福地 悠太様

【ご経歴】
ブティックファームにて主に上場企業に対するストック・オプションの設計・導入支援、エクイティ・ファイナンスに関するアドバイザリー業務、M&Aアドバイザリー業務等に従事。証券株式会社での投資銀行部門立ち上げを経て、再びコンサルティング業に戻り、株式報酬制度の設計・導入支援、役員報酬制度の設計、指名報酬委員会の設置・運用に係る助言業務等を行う。2024年より役員報酬・株式報酬制度コンサルティングを専門とするO f All株式会社(https://ofall.jp/)を設立。
聞き役:㈱セレブレイン 代表取締役社長 高城幸司